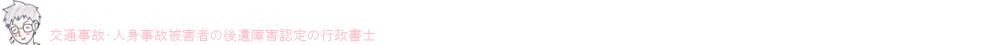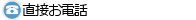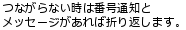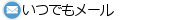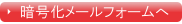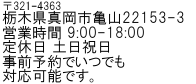症状固定を迎え、いよいよ後遺障害診断書を書かれる、これが、今後の賠償を左右すると思うと、不安が隠しきれなくなるのは、当然のことではないでしょうか。
当然、医師に、ありもしないことを書いてくれ、と言えるはずはありませんが、必要なことが、うまく伝えられないのも事実。
少なくとも、出来上がった後遺障害診断書の確認すべきポイントが把握できれば、過剰な不安に襲われずに済むのではないでしょうか。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
後遺障害診断書を書くのは、当然、医師です。
柔道整復師に書いてもらうことはできません。
また、事故受傷後から、症状固定日まで、一貫して同じ医師に診てもらえていれば、その医師に後遺障害診断書を書いてもらえばよいのですが、そうもいかないことがあります。
そう、複数の病院で受診した場合です。
その場合は、治ゆ、症状固定時まで受診していた医師となります。
複数の病院で受診した場合は、通常、最後に診療を受けた病院で、後遺障害診断書を書いてもらうべきです。
後遺障害診断書は、症状固定に基づき、後遺障害について書くものですから、症状固定当時の、最終の医療機関の医師に書かれるべきなのは当然です。
しかしながら、転院先の病院、医師は、初診の医師からの紹介状によって当初の傷害の内容を知るか、或いは被害者の訴えによって、傷害の内容を確認して診療するので、後遺障害の原因である傷害内容と事故との因果関係の判断は、初診の医師に比較して困難といえます。
そうすると、実は、一般的には、転院した場合、転院先の病院から「最初の状態がわからないので、最初にかかった病院に後遺障害診断書を書いてもらうように」と言われることになります。
ところが、転院元の病院は、転院のきっかけ、経緯によっては、後遺障害診断書を書いてくれないこともあったりするので、これは転院時に、転院先の病院に、その後の後遺障害診断書作成についても確認した上で転院した方がよいこととなります。
この問題は、整骨院にばかり通って、病院に全く行かなかった場合にも発生します。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
後遺障害診断書はA3横用紙となっており、記入すべき事項は決まっています。
それぞれの項目に注意事項も書いてはありますが、ここで細かく見てみようと思います。
大前提としてのお願いの記載
記入にあたってのお願い、というものがあります。まずはこれでこの用紙に求められているものを理解してください。
1、この用紙は、自動車損害賠償責任保険における後遺障害認定のためのものです。交通事故に起因した精神・身体障害とその程度について、できるだけくわしく記入してください。
2、歯牙障害については、歯科後遺障害診断書を使用してください
3、後遺障害の等級は記入しないでください。
1に「できるだけくわしく」とお願いされているにも関わらず、非常に大雑把な記載のされ方をすることが多いです。
2は、歯牙障害は、別の用紙があるのです。
3は、労災は医師が等級について言及することになっていますが、自賠責はそうではないためのお願いです。
個人情報
氏名・性別・生年月日・住所・職業
これは当然の記載事項ですね。
怪我のこと・治療のこと
受傷日時・症状固定日
当院入院期間・当院通院期間
傷病名
既存傷害
自覚症状
この項目も当然の記載事項ですね。
ただし、傷病名は医師の見落としがあったりすると、不足することがあります。
既存障害は、かかりつけ医ならご存じかも知れませんし、本来、被害者本人が医師に伝えるべきことです。
今回事故以前の精神・身体障害の有無を、部位・症状・程度について記載します。
自覚症状は、最初に被害者が不満を感じやすい項目です。
自覚症状は医師にきちんと伝え、ここにきちんと記載されるべきです。
各部位の後遺障害の内容
①精神・神経の傷害 他覚症状および検査結果
②胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害
③眼球・眼瞼の障害
④聴力と耳介の障害
⑤鼻の障害
⑥そしゃく・言語の障害
⑦醜状障害(採皮痕を含む)
⑧脊柱の障害
⑨体幹骨の変形
⑩上肢・下肢および手指・足指の障害
ここは、後遺障害になるかもしれない症状について、部位別に記載する項目です。
当然、交通事故外傷と全く関連がない項目に記載を求める必要はありません。
各部位の障害について、該当項目や有・無に〇印をつけ①の欄を用いて検査値等を記入してください、と記載あることにお気づきでしょうか。
このお願いがあるのになお記載しないということは、検査をしていないということではなく、検査をした上で記載を省略していると、自賠責保険に受け止められかねないことに注意してください。
現実には、傷病名、自覚症状からみて、情報が不足していると感じれば、自賠責保険から意見書を求められることがありますが、逆に言えば、傷病名や自覚症状の記載に不備があり、かつ、この項目に不足があるならば、自賠責保険には事実と異なる印象を与え、ズレた判断がされるということです。
さらに以下のような記載もあります。
知覚・反射・筋力・筋萎縮など神経学的所見や知能テスト・心理テストなど精神機能検査の結果も記入してください
X-P・CT・EEGなどについても具体的に記入してください
眼・耳・四肢に機能障害がある場合もこの欄を利用して、原因となる他覚的所見を記人してください
X-PやCTなどの画像所見について、見れば誰でもわかる怪我であっても、ここに記載がなければ、自賠責保険は無かったものとして扱います。
例えば、骨折をしていて、画像で明らかであっても、ここに記載がなければ、骨折をしていないか、事故前の状態に完全に戻ったとして扱います。
変形癒合が見て取れてもなお、無視か見落としをされてしまうと思ってください。
医師は、画像をみればわかるからと、省略したがりますが、この用紙を見て判断する人は、医師ではありません。
医師には子供に説明するかのような気持ちになってもらい、記入してもらうことが大切です。
②以降の項目については、当サイトの後遺障害診断表を部位別に見ていただければ、意味や記載が必要な理由はご理解いただけると思います。
障害内容の憎悪・緩解の見通しなどについて記入してください
ここの記載もトラブルにの火種になりやすい部分ではあります。
緩解とは本来「病気の症状が、一時的あるいは継続的に軽減した状態。または見かけ上消滅した状態」をいい、治ることとは意味が違います。
医師は当然、この本来の意味でこの言葉を理解し、この欄に必要事項を記入するでしょう。
一時的に症状が消滅する可能性があることも、緩解ですから、それすらをも緩解と表現するでしょう。
しかし、自賠責保険は、おそらく、この緩解と言う言葉の意味をあなたと同じ意味でとらえています。
例えば、専門家と、そうでない人とでは「悪意」という言葉にまったく別の意味を持たせているのと一緒です。
専門用語で問いかける割には、自賠責保険は専門用語の意味をさほど理解していません。
しかも「かんかい」は緩解よりも「寛解」の表記の方が一般的なようです。
その点も、見る人は素人、ということをよくよく医師にご理解いただいて記入してもらう必要があります。
診断日・診断書発行日・診断者名
ここが問題になることはほとんどないでしょう。もしあっても、それは単なる誤字か何かですから、これまで説明してきた診断内容や見通しと比べれば、医師も訂正印で直してくれますし、それでOKです。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ
後遺障害診断書に問題があった場合はどうすればよいのでしょうか。
医師によっては、訂正印にて、修正をしてもらえることがあります。
不足を補う場合は、意見書を書いてもらう、セカンドオピニオンを受けるなどの方法があります。
いやらしいと思われることを恐れずに言うなら、専門家を頼る、という方法も。
| 交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
|
| 交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ |
▲ このページの先頭へ